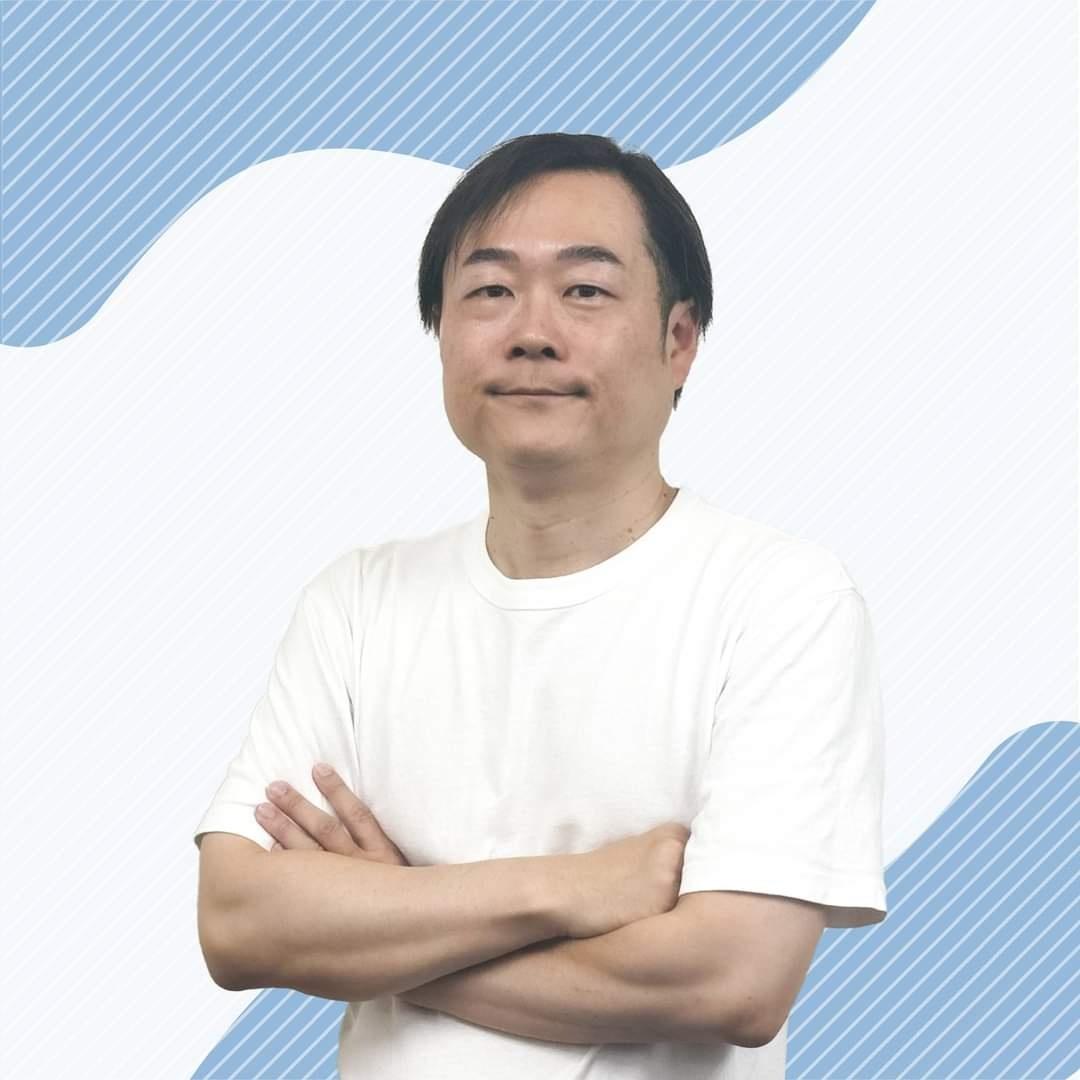ホームページ保守の費用相場と外注先選び|障害対応・セキュリティ強化の勘所
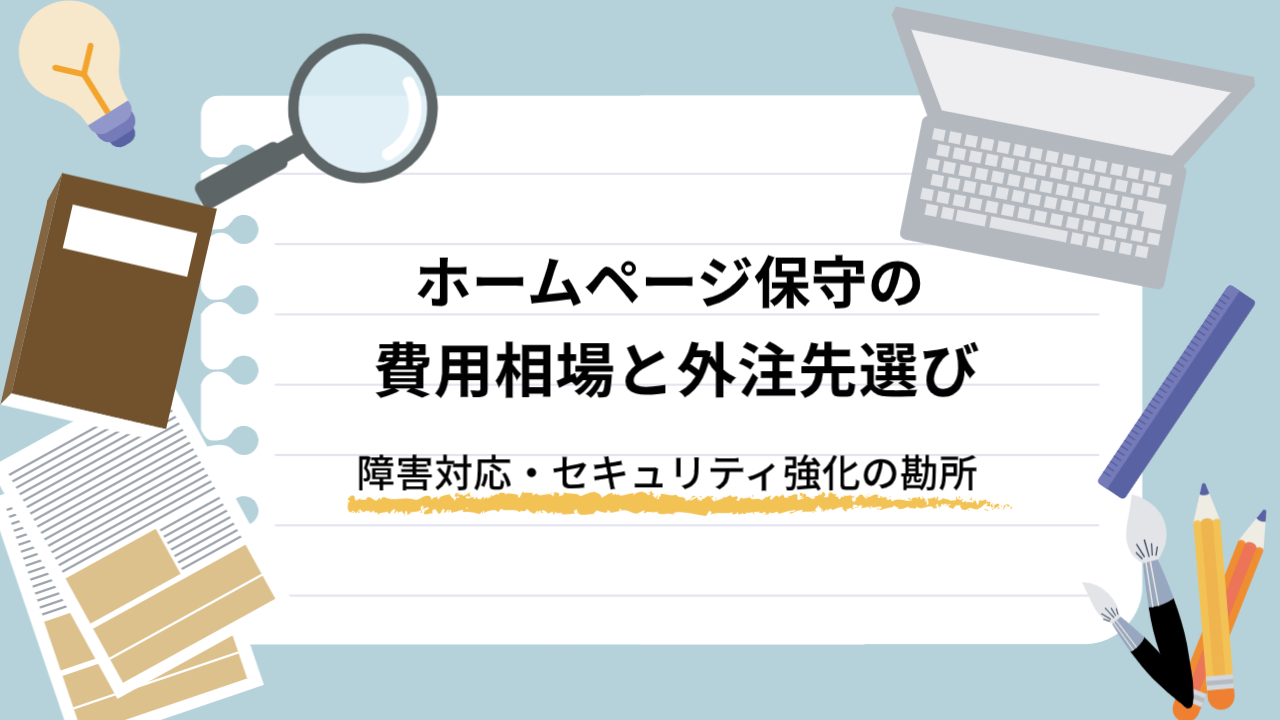
バックアップを怠って表示崩れが長時間放置されたり、脆弱性パッチを当て忘れて改ざん被害を受けたりするケースが後を絶ちません。
ところが保守費用は月額数千円から数十万円まで幅広く、内容も会社ごとに大きく異なるため、適正価格をつかみにくいのが実情です。
この記事では、保守費用の相場を「サイト規模・CMS・サーバー構成」の3要素から整理し、障害対応やセキュリティ強化でおさえるべき勘所をまとめます。
内製と外注のメリット・デメリットを比較したうえで、最後におすすめ外注先5社を紹介します。
CONTENTS
保守を甘く見ると何が起こるか

公開してからのホームページには改ざんや表示崩れ、検索順位低下といったリスクが常に付きまといます。
バックアップや脆弱性パッチを後回しにすれば、障害復旧に数十時間を要し、潜在顧客や取引先の信頼を一瞬で失うことも珍しくありません。
保守はコストではなく、損失を避けるための最低限の投資と位置づける必要があります。
代表的なトラブル3選
- 改ざんやマルウェアの埋め込み
管理画面のパスワードが弱いまま放置し、ファイルを書き換えられると検索結果に「危険なサイト」と表示され、流入がほぼゼロになることがあります。 - 表示崩れ・リンク切れの放置
CMS やプラグインを更新せずにバージョンが古くなると、レイアウトが崩れたりフォーム送信ができなくなったりします。ユーザーは不信感を抱き、最悪の場合は競合他社へ離脱します。 - 検索順位の急落
ページ速度低下やスパムリンク注入を放置すると、Google から品質が低いと判断され順位が大きく下がることがあります。
保守の目的
- サイトを安全に保つ脆弱性パッチ適用や WAF 導入で不正アクセスを防ぎます。
- ユーザー体験を維持する バックアップからの迅速復旧やモバイル表示の最適化で離脱を防ぎます。
- 検索評価を守る 常時 SSL、表示速度改善、構造化データの更新などテクニカル SEO を継続します。
具体的に得られるメリット
- 障害対応の人件費と機会損失を最小化できる
- インシデント発生時に証跡と手順が明確で復旧が早い
- セキュアな運用体制を示すことで取引先の信頼を高められる
保守はコストではなく“保険兼投資”と考えると、月額数万円の費用がトラブル時の損失を大きく上回るケースが多いとわかります。
費用相場の基本構造

料金は契約形態・サイト規模・CMSの種類・サーバー構成など複数の要素で決まります。
ここでは、費用がどのような仕組みで算出されるのかを整理します。
月額固定と時間課金の違い
一般的な保守契約は、あらかじめ作業内容を決めて毎月一定額を支払う月額固定型と、依頼した分だけ支払う時間課金型に分けられます。
月額固定型は突発的な作業が発生しても費用が変わらない安心感がありますが、
想定を超える大規模トラブルは別途見積もりになる場合があります。
時間課金型は依頼頻度の少ないサイトに向いていますが、障害が重なるとコストが膨らみやすい傾向があります。
サイト規模とトラフィック
ページ数が多い、アクセス数が多い、画像や動画を大量に扱うといった条件ではバックアップ容量や監視ポイントが増えるため、保守工数が高くなります。
目安として小規模(~50ページ)のコーポレートサイトで月額1万~3万円、
中規模(数百ページ)のメディアで月額3万~10万円、大規模ECやポータルでは10万円を超えるケースが目立ちます。
CMSとカスタマイズの影響
WordPressやEC-CUBEなど普及率の高いCMSはプラグインやアップデートの手順が確立しており、比較的コストを抑えやすいです。
一方、独自開発のプラグインが多かったり、ヘッドレスCMSやスクラッチ開発で
高度なカスタマイズを行っている場合は、検証環境の用意や個別テストが必須になり費用が上がりやすくなります。
サーバー構成と冗長化
共用レンタルサーバー、クラウドVPS、フルマネージドのコンテナ環境など、インフラ構成によって保守内容が変わります。
冗長化構成やCDNを利用している場合は、複数ノードの監視やログ解析が必要になるため工数が増えます。
クラウドの場合はOSパッチ適用やオートスケール設定の調整も保守範囲に含めるかどうかを確認したほうが安心です.
追加オプションで変動する費用
脆弱性診断レポート・WAF運用・24時間365日の有人監視・ページ高速化チューニング・SEOテクニカル改善などは基本プラン外で個別に加算されることが多いです。
オプションを組み合わせると、基本料金の1.5~2倍程度に膨らむことも珍しくありません。
こうした要素を分解して見積もりを比較すると、自社のサイトに何が必要で、どこに費用が掛かっているのかが見えやすくなります。
標準メニューと担当範囲

緊急時に発生するコストや手戻りを抑えやすくなります。
基本プランに含まれやすい作業
定期バックアップの取得や CMS・プラグインのマイナーアップデート、SSL 証明書の更新、サーバーの死活監視といったインフラ寄りのタスクは、
多くの制作会社で月額料金に組み込まれることが多いです。
月次レポートもこの範囲に含まれるケースが増えており、アクセス状況やエラーログを共有しながら改善提案を受けられます。
追加オプションになりやすい作業
脆弱性診断や WAF のチューニング、24 時間 365 日の有人監視などは、
専門スキルと夜間人員を必要とするため、別料金での提供となる場合が一般的です。
CMS のメジャーアップデートや PHP バージョンの切り替えも、事前検証と改修を伴うため個別見積もりが求められることが多いです。
マーケティング寄りの作業として、バナー差し替えや meta タグ最適化を依頼する場合は、チケット制や時間単価制で精算される傾向があります。
社内と外注の役割分担
バックアップデータの保管や障害発生時の一次判断を社内で行い、復旧やパッチ適用を外注へ委ねるなど、責任範囲をあらかじめ線引きしておくと連絡がスムーズです。
緊急連絡先や優先順位を共有ドキュメントにまとめ、担当者交代があっても
対応に迷わない環境を整えておくと、トラブル時の混乱を最小限に抑えやすくなります。
セキュリティ強化のポイント

ここでは、保守作業と合わせて検討しておきたい五つの安全対策を、できるだけ分かりやすい言葉でまとめます。
WAFを置いて攻撃をはじく
WAF(Web アプリケーションファイアウォール)は、サイトへの不正なアクセスを門番のようにブロックする仕組みです。
クラウド型なら月数千円から使え、導入したあとは“本物のアクセスかどうか”を自動で振り分けてくれます。
設定が合わないと正常なアクセスも止めてしまうため、調整作業が月額に含まれるか確認すると安心です。
脆弱性診断で弱い所を洗い出す
脆弱性診断は、サイトに潜む“攻撃されやすい穴”を探す健康診断のようなものです。
専用ツールで自動チェックを行う簡易診断なら数万円、専門スタッフが手動で疑似攻撃を行う本格診断は十万円以上かかることが多いです。
診断報告に対策方法が書かれているかも確認したいポイントです。
ログインを二重ロックにする
管理画面へ入るとき、ID とパスワードに加えて SMS や認証アプリでコードを入力する
“二要素認証”を設定すると、パスワードが漏れても不正ログインを防げます。
あわせて、管理画面に入れる人を最小限に絞り、使わないアカウントはこまめに削除しておくと安全です。
アップデートのタイミングを決めておく
WordPress やプラグイン、サーバーのソフトは新しいバージョンが出たら早めに更新することが大切です。
更新前にテスト用サイトで表示崩れがないか確認し、問題がなければ本番へ反映する流れをルール化しておくと失敗を減らせます。
もしものときの手順を用意する
万一サイトが止まったり改ざんされたりした場合に備え、誰がどこへ連絡し、どのバックアップを戻すかを書いた手順書を用意しておきます。
アクセスログやエラーログは少なくとも3か月分は保存しておくと、原因調査がしやすくなります。
障害対応フローと SLA

対応手順と保証水準(SLA)が事前に決まっていると、混乱や責任の押しつけ合いを避けやすくなります。
障害発生から復旧まで
監視ツールが異常を検知すると、担当者にアラートが届きます。まずはサイトの表示とログを確認し、攻撃か機器故障かを切り分けます。
原因が分かったら、バックアップ復元や設定の元戻しでサイトを正常化し、最後にログを整理して再発防止策を決めます。
SLAで見る3つの数字
- 応答時間:アラート受信から対応開始までの上限
- 復旧時間:障害発生から正常復帰までの上限
- 稼働率:月間でサイトが利用可能だった割合
目標値が契約書に明記され、達成できなかったときの補償内容が書かれているかを確認すると安心です。
契約前のチェックポイント
一次対応が「連絡のみ」か「暫定復旧まで」かを質問します。
夜間や休日の窓口が一本化されているか、担当エンジニアと直接やり取りできるかも要確認です。
罰則条項の有無と補償の範囲を把握しておくと、費用とリスクを読み違えにくくなります。
内製と外注の比較

ここでは、代表的なメリット・デメリットと、両者を組み合わせたハイブリッド体制について整理します。
内製の特徴
社内に担当者を置くと、更新依頼や障害報告をすぐに伝えられ、ちょっとした修正をその日のうちに行える強みがあります。
開発の経緯やコードの癖を理解したメンバーが作業するため、調査に時間を取られにくい点も利点です。
一方で、担当者が異動や退職をすると保守のノウハウが途切れやすく、夜間や休日の緊急対応では人手を確保しづらくなる傾向があります。
教育にかかる費用と担当者の負担を、どのようにバランスよく保つかが課題といえます。
外注の特徴
専門会社に任せると、24 時間監視や脆弱性診断など高度な作業をまとめて依頼でき、担当者交代による品質低下も起こりにくくなります。
障害復旧のフローが整備されているため、休日や深夜でも一定の応答時間と復旧時間が保証される点が安心材料です。
反面、軽微な修正でも見積もりや発注手続きが必要な場合があり、社内で完結する作業より時間がかかるケースがあります。
コストも固定費化しやすいので、実作業の頻度を見ながら契約内容を適切に調整することが求められます.
ハイブリッド体制の考え方
日常的なテキスト修正やページ追加は社内で対応し、バックアップ・監視・脆弱性パッチといった
インフラ寄りの作業を外注へ委託する形にすると、スピードと専門性を両立しやすくなり、
社内担当者が外注先の一次窓口を兼ねると連絡が一本化されるので、緊急時の判断も迷いにくくなります。
役割分担を明確にし、作業手順書や連絡フローを共有すると、体制変更があっても品質を維持しやすいです。
外注先選びのチェックリスト

項目が多すぎると比較が煩雑になるため、押さえておきたいポイントを4つに絞って整理します。
作業範囲と追加料金の線引き
まずは月額料金に含まれる作業と、別料金となる作業を具体的に聞くことが大切です。
たとえば「マイナーアップデートまでが基本」「メジャーアップデートは別見積もり」「復旧後の改修は工数計算」
のように境界を文書で示してもらうと、トラブルを回避しやすくなります。
SLAと対応体制
応答時間・復旧時間・稼働率といったサービス水準が数値で提示されているかを確認します。
深夜や休日の連絡窓口が電話、メール、チャットのどれに対応しているか、一次対応を誰が行うかを明確にしておくと安心です。
セキュリティとバックアップの方針
WAFや脆弱性情報の収集方法、ログ保管期間などを質問し、会社のセキュリティ意識を見極めます。
バックアップは取得頻度と保存先、テスト復元の有無まで確認すると、万一のときに復旧までの時間を把握できます。
契約更新と引き継ぎ条件
最後に、契約更新のタイミングと解約予告期間、違約金の有無を確認します。
将来内製へ切り替える可能性がある場合は、ソースコードや設定ファイルをどの形式で受け取れるか
引き継ぎサポートがあるかどうかも聞いておくと後々の移行がスムーズです。
ホームページ保守を任せたいおすすめ企業5選
保守を外注するなら、障害対応力・セキュリティ体制・実績の3つを軸に比べると選びやすくなります。
ここでは総合力の高い企業から専門特化型まで、特に評価の高い5社をピックアップしました。
サイト規模や求めるサポート範囲に合わせて、最適なパートナー探しの参考にしてください。
株式会社ファーストネットジャパン

株式会社ファーストネットジャパンは、企画・制作から公開後の運用まで一気通貫で支援する体制を持ち、
保守では WordPress など CMS の更新代行・脆弱性パッチの適用・SSL 更新・24 時間監視・自動バックアップ復元までをワンストップで対応します。
WAF のチューニングや簡易診断といったセキュリティ強化も相談でき、障害時は暫定復旧と原因報告をセットで進める進行が特徴です。
月次レポートではアクセス・エラーログ・改善提案をまとめ、
速度最適化やフォーム離脱の対策まで踏み込んだ運用改善につなげやすい点が評価されています。
社内担当者向けの更新レクチャーも用意し、内製と外注の分担を柔軟に設計しやすいところが魅力です。
| 会社名/サービス名 | 株式会社ファーストネットジャパン |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区南久宝寺町1-7-10 シャンクレール南久宝寺201 |
| 設立年月 | 2004年12月 |
| 公式サイト |
株式会社ZoDDo

株式会社ZoDDo(ゾッド)は、名古屋市東区と春日井市を拠点に、ホームページ制作と保守運用をワンストップで提供する制作会社です。
公開後の“育てる運用”を重視し、WordPress を中心とした CMS のバージョン管理・テーマ/プラグインの検証・SSL 更新・バックアップの世代管理・死活監視といった基本タスクを地道に実行します。
更新作業はステージング環境で事前確認を行い、レイアウト崩れやフォーム不具合の発生を未然に抑える体制です。
制作面ではコーポレート/採用/医療・クリニック/製造業など幅広い業種に対応し、サイトの目的に合わせて情報設計とデザインを最適化。
看板・冊子・ロゴなどオフライン領域も手がけるため、ブランドトーンを統一したコンテンツ運用に発展させやすい点も魅力です。
| 会社名/サービス名 | 株式会社ZoDDo |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市東区代官町23-11 安田第3ビルフローレス代官202 |
| 設立年月 | 2012年2月 |
| 公式サイト |
株式会社ZeroPlus

株式会社ZeroPlusは札幌を拠点に、Web サイト制作と Web/モバイルアプリ開発を手がけるチームです。
Flutter によるクロスプラットフォーム開発で培った設計・品質管理の知見を、Web サイトの保守運用にも展開。
CMS 更新やテーマ整備、パフォーマンス改善、CDN 導入支援、アクセス監視・バックアップといった基本を押さえつつ、
アプリや管理画面などシステム寄りの保守もワンストップで対応できます。
SNS 運用・映像制作・AI 業務効率化の支援メニューも持ち、Web コンテンツと外部チャネルを横断した運用サイクルを組み立てやすいのが特長です。
地方発ながら広域対応に慣れており、スピードと柔軟性を両立した伴走が期待できます。
| 会社名/サービス名 | 株式会社ZeroPlus |
|---|---|
| 所在地 | 北海道札幌市中央区南8条西12丁目2番10号 |
| 設立年月 | 2022年9月 |
| 公式サイト |
株式会社プライドアーク
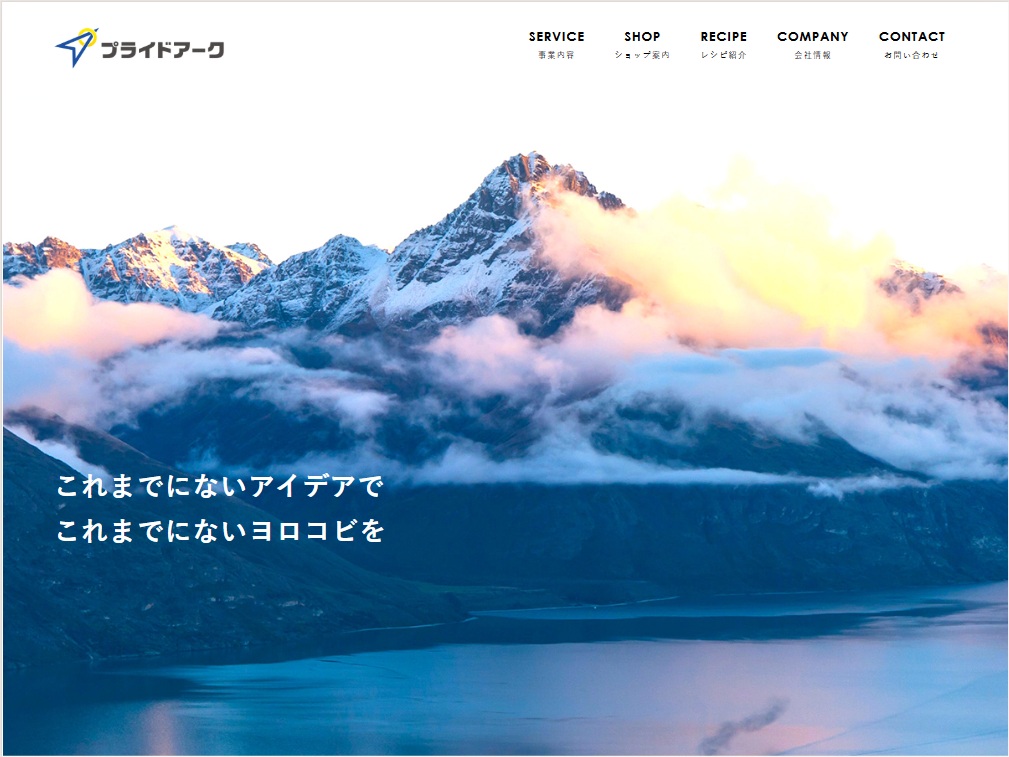
株式会社プライドアークは宮城を拠点に、Web デザイン制作と運用、採用ブランディングなどを展開する会社です。
Web 制作では「企画→制作→運用→改善」を一体で捉え、公開後の運営まで見据えた戦略的な設計を重視。
保守面では CMS 更新、ステージングでの事前検証、バックアップ/監視、フォームや計測タグの点検など“壊れない運用”の基本を丁寧に実施します。
飲食・EC の運営ノウハウも持つため、コンテンツ更新や撮影・コピー制作を含む継続改善に強く、地域ブランドや店舗サイトの育成にも適しています。
仙台市の店舗運営や EC 構想など実業で得た学びを、Web 運用の改善に還流できるのがユニークな持ち味です。
| 会社名/サービス名 | 株式会社プライドアーク |
|---|---|
| 所在地 | 宮城県塩竃市後楽町8-7 |
| 設立年月 | 2020年6月 |
| 公式サイト |
株式会社リクト

株式会社リクトは福岡市中央区を拠点に、制作・運用・営業DX を一体で提供する体制が特長のWeb制作会社です。
計測環境の整備とレポーティングにも力を入れており、アクセス解析や検索コンソールの指標、コアウェブバイタルなどを踏まえた
速度最適化・構造化データ整備・フォーム改善を継続提案。
さらに SEO・広告運用・MEO といった集客施策、CRM導入やDX研修 まで含めた営業プロセスの最適化支援にも対応しているため、
サイトを“作って終わり”にせず成果につなげたい企業と相性が良いパートナーです。
2012年設立以来、コーポレートや採用、サービスサイトなど中小企業を中心に幅広い業種を支援し、
「わかりやすい情報を探しているすべての人へ」という理念のもと、運用現場で迷わないガイドと管理画面設計を整えている点も安心材料です。
| 会社名/サービス名 | 株式会社リクト |
|---|---|
| 所在地 | 福岡県福岡市中央区大名1丁目9-27 第一西部ビル306 |
| 設立年月 | 2012年1月 |
| 公式サイト |
まとめと次のステップ

ホームページ保守は、公開後の安全と信頼を維持するための欠かせない投資です。
費用だけでなく、対応範囲と体制を把握しておくことで、もしもの時の損失を抑えやすくなります。
保守で押さえる3つの要点
定期バックアップ・監視・脆弱性パッチの「基本三点」を欠かさないことが第一です。
次に、応答時間・復旧時間・稼働率で示される SLA が数値で定義されているかを確認すると安心できます。
最後に、月額内と追加料金になる作業を契約書で切り分けておくと、緊急時の請求トラブルを避けやすくなります。
ベンダー選定の3段階
はじめに社内で保守目的と年間予算を共有し、必要な作業を一覧に整理します。
次に、その要件を RFP にまとめ、複数社へ同じ条件で見積書を依頼します。
最後に、SLA と補償内容を比較し、サイト規模やセキュリティ要件に合うパートナーを決定します。
運用フェーズの3つの習慣
契約後は手順書と緊急連絡網を全関係者に共有し、担当者交代時の引き継ぎをスムーズにします。
月次レポートでログと改善提案を確認し、優先度の高い項目から実施すると効果が見えやすくなります。
半年ごとに保守内容と費用を見直し、不要なオプションの削減や新規対策の追加を検討すると、コストと安全性のバランスを保ちやすくなります。
ホームページ保守は、表に見えにくいもののビジネスの信頼と収益を支える要となります。
定期バックアップや脆弱性対策に加え、SLA で担保された迅速な障害対応を仕組み化しておくことで、
サイトは常に安全かつ快適な状態を保ちやすくなります。
結果としてユーザー満足度が向上し、問い合わせや売上、採用エントリーといったビジネス成果の底上げが期待できます。
今回紹介したポイントと企業選びの視点を参考に、自社に最適な保守体制を整え、長く愛されるウェブサイトを育てていただければ幸いです。